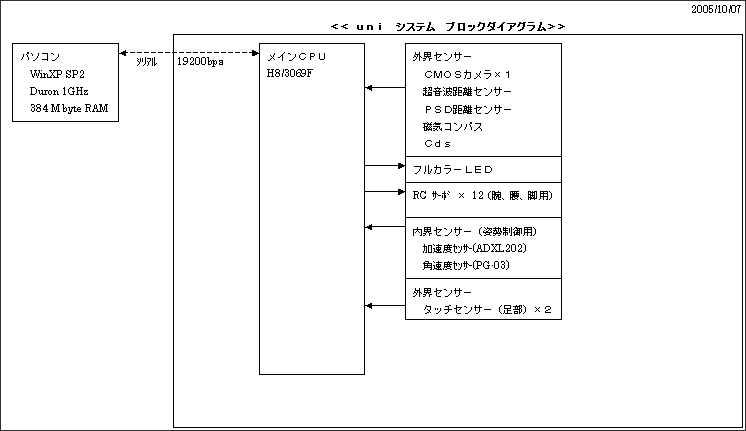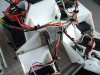はじめはロボット内臓CPUを秋月のH8/3069マイコンボード1つに集約し、CPU間通信に関する部分を
省き、全体的にW6簡略化したような形にしました。搭載マイコンを過不足なく使い切ることを目指しました。
作っているうちに1つのマイコンでは足りなくなってきたので、結局胸部フレームを大きめに作り直し、RCサーボ他
とのI/Oを担当するサブCPUを2個加え、W6と同じ様なアーキテクチャに戻りました。


|
05.09.03:CPUボード(v1)
胸の中に秋月のH8/3069Fのマイコンボードが入っています。I/Oボードの上には
信号のレベル変換の回路と、電源IC(3.3Vと12V用)等が載っています。
|

|
メインCPU用I/Oボード新旧比較
上が「v1」、下が「v2」です。ちょっとすっきりしました。
|

|
配電基板
動力系(RCサーボ用)の電源線を集合させるための基板です。
上半身と下半身に1個ずつ付いています。エッチング用の全面銅箔の基板から作りました。
|

|
ジャイロ
ジャイロは腰に、両面テープで貼り付けてあります。ゲインと中立位置をドライバーで
調整できるように、上面は空けてあります。
|

|
操作盤
左のディップスイッチでモードを指定し、右のタクトスイッチでスタート(アボート)します。
中央のUSBのコネクターはRS232の通信用コネクタです。PCに接続します。
「ランドセル」の中に付いています。
|

|
CPUボード(装備状態 v1)
|

|
CPUボード(装備状態 v2)
手前(背中側になります)がNo.2サブCPUで奥がメインCPUです。
|

|
No.1サブCPU(装備状態 v2)
腰の辺りに付いています。
当初の意図のとおり、腰関節をまたぐ配線の本数は少なくなったのですが、やはり腰の周囲の配線が
「ぐちゃぐちゃ」な感じになってしまいました。
|

|
メインスイッチ
制御系電源(CPUボードやセンサ用)のスイッチです。
|

|
動力系のスイッチ
左肩の後ろに付いています。
センサー関係のプログラムをテストするとき等、RCサーボの電源をカットして消費電力を下げたいとき
は、このスイッチでDC/DCコンバータを待機状態にします。
|
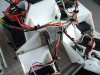
|
RCサーボの配線
自動車の「ハーネス」の要領でまとめて、背中側に敷設してあります。
|